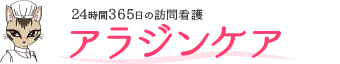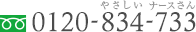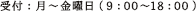結婚式の付き添いで親子を支える
「難病の妻を結婚式に出席させたい」というご主人の切なる願い
人生の伴侶を得て、新たな門出を祝う結婚式。それは、育ててもらった親に感謝を捧げるセレモニーでもあります。しかし、晩婚化の影響で、新郎新婦の親の高齢化も進む一方。公共施設のバリアフリー化が進んだとはいえ、外出のために公的な看護・介護サービスを利用しようとすると、まだまだ制約が多いのが現状です。このため、疾患や障害を抱えているために、我が子の結婚式への出席をあきらめざるをえない親御さんも少なくありません。
アラジンケアならば、看護師のサポートにより、安心・安全な外出を実現します。本事例は、難病と認知症を疾患として抱えるお母様が、看護師に付き添われて、息子さんの結婚式への出席を果たしたケースです。
70代女性のEさんは、パーキンソン病の進行により、ほぼ寝たきりの状態でした。介助なしではベッドから起き上がることもできず、同時に認知症も日ましに進行。ご主人や息子さんに対しても、唸り声や口の動き、表情などで、なんとか意志を伝えているような状態でした。
そんなEさん夫妻のもとに、うれしいニュースが舞い込んできました。手塩にかけて育てた息子さんが、ついに結婚することになったのです。Eさんのご主人は、「息子の晴れの姿を、どうしても妻に見せてやりたい」と考えました。しかし、挙式当日は“新郎の父”として、お客様をもてなさなければならない立場。式場に車椅子のEさんを連れて行っても、付ききりで世話をすることはできません。
看護師に付き添われ、車椅子で式場へ
そこで、知り合いのケアマネージャーに相談したところ、紹介されたのが、自費の看護サービスであるアラジンケアでした。このサービスなら、場所が結婚式場であっても、日曜祭日でも、長時間の看護師の付き添いを頼むことができます。
これで、安心して妻を結婚式に連れて行ける――Eさんは、ホッと胸をなで下ろしました。
式の前日から、Eさん夫妻は会場のホテルに宿泊。ご主人はEさんを不安にさせないよう、普段使用している医療器具やケア用品を、可能なかぎりホテルの部屋に持ち込みました。バッテリー式の吸引器や吸引用カテーテル、薬用コップ、経管栄養用のボトルから、防水シーツや毛布、バスタオル、おむつに至るまで、大量の荷物をホテルの部屋に搬入しました。アラジンケアの看護師もホテルまで同行し、物品の搬入と荷解きをお手伝いしました。
荷解きを終えたあと、看護師は下見のため式場に直行。担当のウェディングプランナーに館内を案内してもらい、挙式当日、Eさんが車椅子で移動する予定のコースをくまなく見て回りました。
式場によっては、屋外での写真撮影の際、庭園の砂利に車椅子のタイヤがとられて動けなくなることがあります。また、患者様の気分が悪くなったときに、休憩スペースが確保できず慌ててしまったことも。こうした事態を未然に防ぐためにも、事前の下見は必要でした。
結婚式当日、ホテルの部屋で朝のケアを受けたEさんは、晴れ着に身を包んで親族の控え室に向かいました。ここで懐かしい人々と旧交を温めたあと、結婚式に参列。挙式の間中、ご主人に見守られながら、車椅子に静かに座っておられました。また、看護師も、チャペルの端に座ってEさんの様子を看守りながら、目立たぬように控えていました。
息子からの手紙に、思わず涙が…
式の後は、待ちに待った結婚披露宴です。テーブルには新郎新婦から列席者に宛てた手紙が置かれ、ご主人が手紙を読んで聞かせると、Eさんの目に涙が浮かびました。
披露宴では、新郎新婦の誕生からゴールインまでの軌跡を映したスライドショーが上映されました。それを見ながら、Eさんは時折、声を立てて笑いました。息子の成長とともにあった楽しく思い出に残る日々。昔の記憶をたぐり寄せながら、2度とは帰らない幸せな日々に、思いを馳せていたのかもしれません。
披露宴が終わり、Eさん夫妻が控え室に戻ると、息子さんが花嫁を連れて入ってきました。そして、ベッドに近づき、優しくEさんの顔をのぞき込みました。
「お母さん。結婚式、無事に終わったよ」
「あ…り・・・が・・・と・・・う」
途切れ途切れに言葉を絞り出したEさんの顔は、ほんのり上気していました。
全てが無事に終わった後、Eさんのご主人は深いため息をつきました。「息子は小さい頃は病弱で、病気をしてはひやひやしたものです。」「その息子が今日のような素晴らしい日を迎えるなんて、本当にうれしい限りです。」と言われました。
病弱だった息子さんを、ありったけの愛情を注いで育ててきたご夫婦だからこそ、夫婦揃って息子の門出を祝いたいという思いも、人一倍強かったのでしょう。
深い絆で結ばれたEさん親子にとって、息子さんの結婚式は、Eさん夫婦二人にとって新しい出発の儀式でもあったのです。ご主人の話を伺いながら、看護師は、胸の中に温かいものが広がっていくのを感じていました。